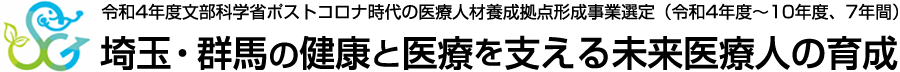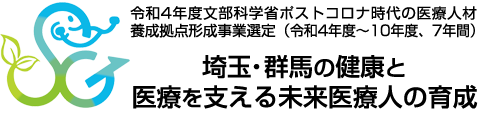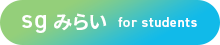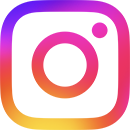学びの報告
| 地域医療とチーム医療1 緩和ケア・グリーフケア特別講義 |
|---|
地域医療とチーム医療のカリキュラム内で「死生にきく/いる・いない・あわい」のタイトルで、学内外の講師による特別講義が開催されました。
緩和ケア医の儀賀先生と、哲学・宗教学が専門の森川先生による対談は、まるでラジオ番組のような雰囲気で、学生もリラックスして「死生観」について考えることができました。


「死」と聞くと、少し怖いイメージがありますが、儀賀先生は「死」について考えることは、より良く生きるために大切だと語ります。
森川先生も、「死」を意識することで、初めて「死生観」という言葉があると言います。人生の価値や意味を深く理解できる、とも語られました。
対談では、大切な人を失った悲しみ(グリーフ)と、そのケアについての話も。 森川先生によると、グリーフは悲しみだけじゃなく、後悔や孤独など、いろんな感情が入り混じった複雑なもの。 儀賀先生は、患者さんとの関わりを通して、グリーフケアの重要性を改めて実感したそうです。
「いる・いない・あわい」ってどういうこと?
「生きている」と「死んでいる」の間には、はっきりとした境界線がない。 森川先生は、この曖昧な「あわい」にこそ、人が生きる意味や価値があるんじゃないかと問いかけます。
そして対談中には、森川先生による詩の朗読と、儀賀先生によるギター演奏という、素敵な時間も! 美しい詩と音楽が、会場を温かい雰囲気に包み込みました。


この対談を通して、改めて「大切なものは人それぞれ」「それを失くした時の感情も人それぞれ」だと感じました。 そして、その「大切なもの」を大切にすることが、より良く生きることに繋がることだと教えていただきました。
今回の講義は、難しく考えがちな「死生観」を、身近な問題として考えさせてくれる大変貴重な時間でした。 これを機に、自分にとっての「大切なもの」について考えてみたいと思いました。